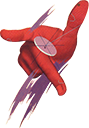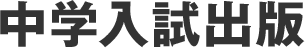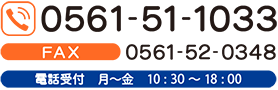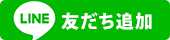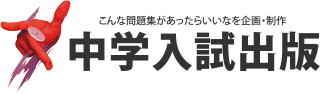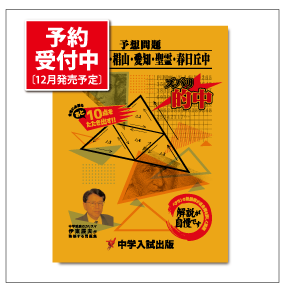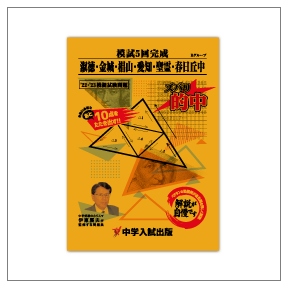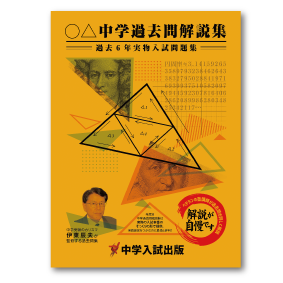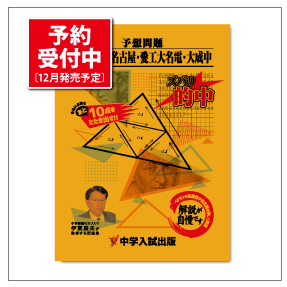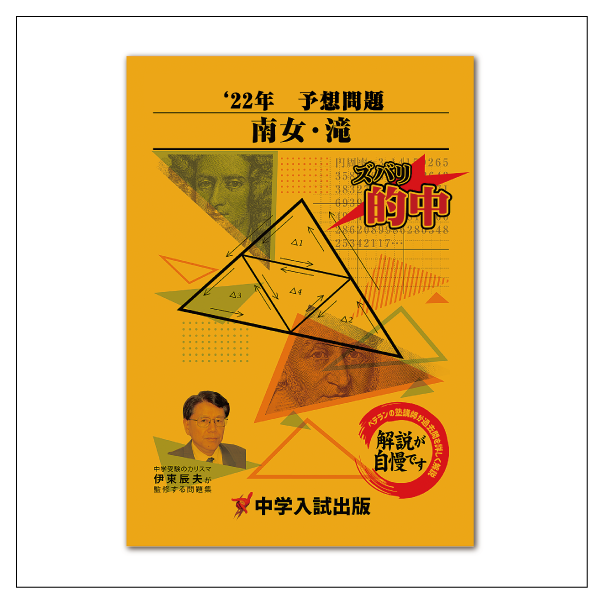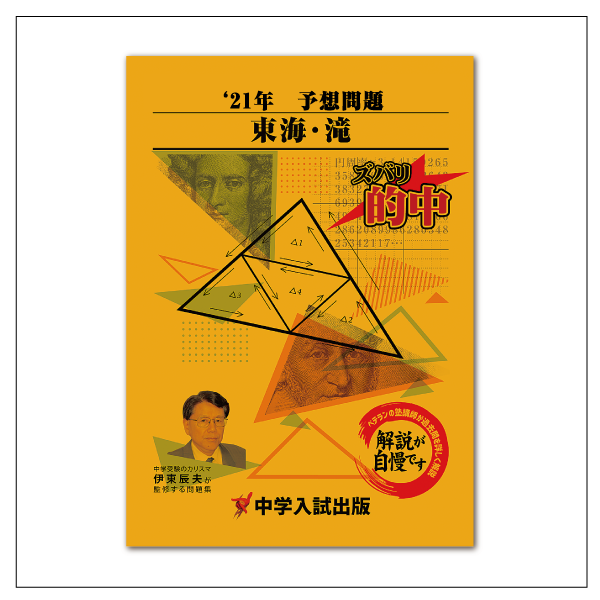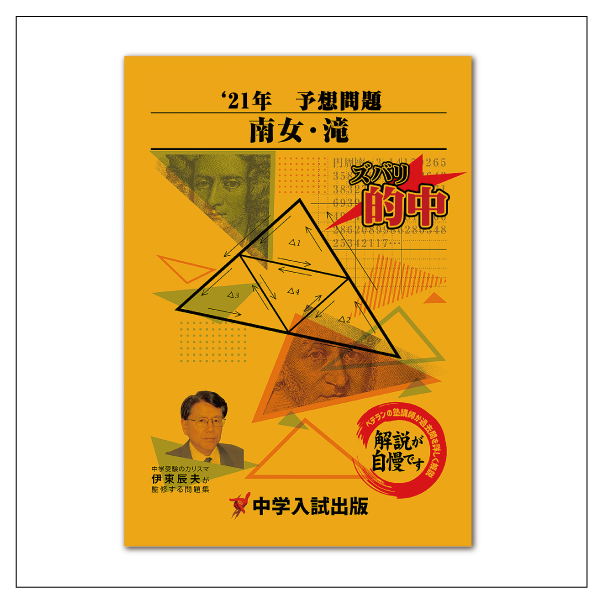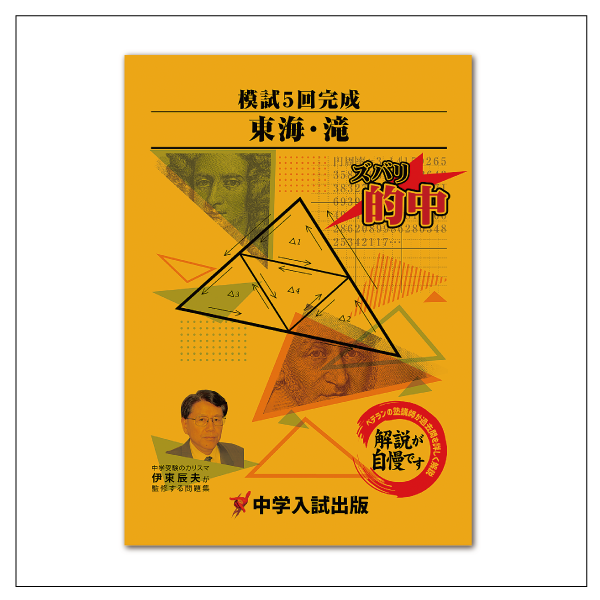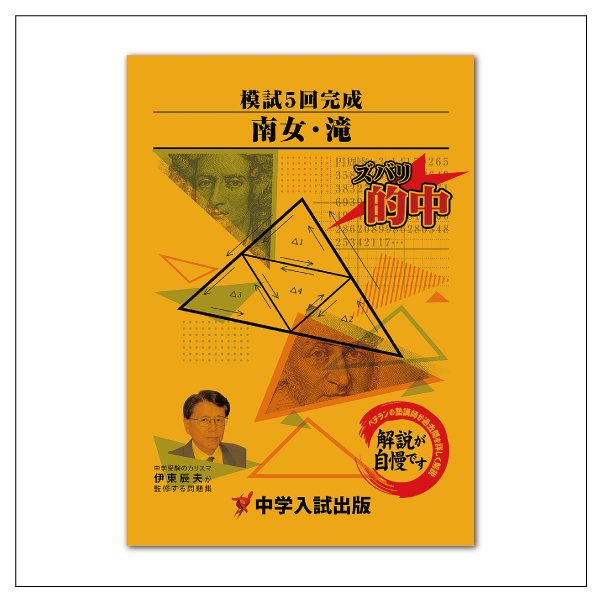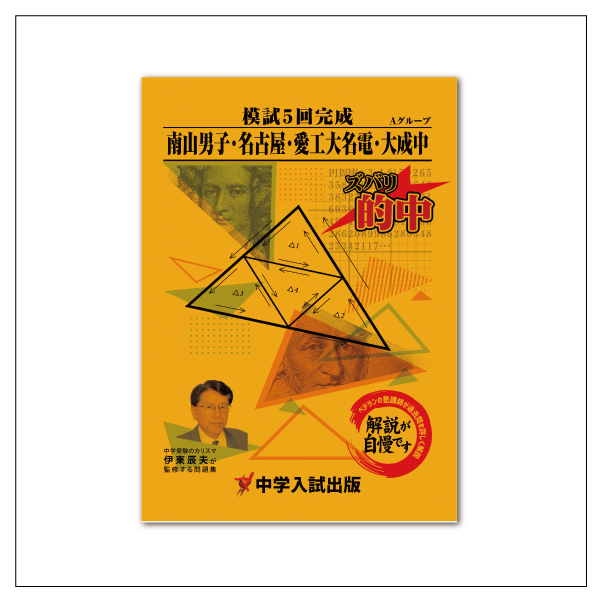春日丘中学校
学校法人 三浦学園 春日丘中学校
〒487-0027 春日井市松本町1105 TEL(0568)51-1115
春日井の私立中学で、小さく入れて大きく育てる方針がモット-で定着している。
当初から進学実績を出し、今では春日井より他地区からの通学が多くなっている。
入学前の学力より入学後の学力を育てる方針が成功しているよい例である。
受験デ-タ-1:応募者数・実質倍率
| 募集人員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
| R5年度 | 105人 | 498人 | 459人 | 302人 | 1.52倍 |
| R6年度 | 105人 | 499人 | 451人 | 324人 | 1.39倍 |
| R7年度 | 105人 | 538人 | 484人 | 284人 | 1.70倍 |
| *(Ⅰ期+Ⅱ期)の合計 | |||||
受験デ-タ-2:受験者平均点 (第1回 Ⅰ期試験)
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 4科総合 | |
| R5年度 | 46.1点 | 59.4点 | 33.3点 | 29.1点 | 167.8点 |
| R6年度 | 57.7点 | 53.6点 | 31.9点 | 28.7点 | 171.8点 |
| R7年度 | 59.1点 | 56.6点 | 34.0点 | 34.1点 | 183.9点 |
| *募集人員は特奨・Ⅱ期合わせて105名 +若干名(年度により異なる)*面接あり。 | |||||
受験デ-タ-3:配点・試験時間
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 面接 | |
| 特奨4科(配点) | 100点 | 100点 | 50点 | 50点 | なし |
| 時間 | 50分 | 50分 | 30分 | 30分 | |
| 特奨Ⅱ期(配点) | 100点 | 100点 | あり | ||
| 時間 | 60分 | 60分 | |||
| *平均点など非公開にて不明 最低点:5割弱がボ-ダ-ライン | |||||
令和7年度入試日程
| 1/6 | 1/11~13 | 1/18 | 1/19 | 1/25・26 | 2/1 | 2/2・8 | |
| 男子校 | 名古屋 | 東海 南山男子 |
|||||
| 女子校 | 名古屋女子A 聖霊VAP 名古屋葵大附 |
金城思考力 聖霊VAP |
愛知淑徳 椙山女学園 |
南山女子 | 名古屋葵大附 | ||
| 共学校 | 星城Ⅰ 大成特 |
名経大市邨B 名経大高蔵 大成専 清林館推・特 |
愛知 名古屋国際グ 愛工大奨学生 名古屋国際A 春日丘Ⅰ |
愛工大一般 名古屋国際B |
大成一般 名経大市邨Ⅱ 名経大高蔵B 春日丘Ⅱ |
滝 星城Ⅱ |
春日丘中学校 おすすめ教材
春日丘中学校の出題傾向
- 算数:傾向と対策
-
春日丘中算数の出題形式は、大問1が「計算の工夫」を含む計算問題5題、大問2が「最小公倍数」などの整数の問題2題、計算分野の「約束記号」、「場合の数」や「仕事算」「速さの問題」などの文章題3題、「円に関する問題」「角度」などの図形問題1題、計8題が出題される。大問3は回転体や立体等の体積問題、大問4は速さや容積などの区分関数(グラフの問題)、大問5は「規則性」「数列」の整数問題が出題される。
図形分野では、「角度」「展開図」「円の問題」「図形の移動」「相似図形」などの問題が中心に出題される。文章題分野では「場合の数」「速さの問題」「仕事算」などが中心に、整数分野では「最小公倍数」「規則性の問題(数列)」、関数分野では「区分関数」が毎年のように出題される。毎年出題パタ-ンが固定されており似通った問題が出題されるので、過去問をしっかり勉強することが合格の鍵となる。
なお、短期間に総復習をしたい人、弱点補強をしたい人、実力を付けたい人には合格問題集をお勧め致します。
- 国語:傾向と対策
-
論説・説明文、物語文の2題構成は例年変わっていません。問題文の字数はやや長い傾向がありますが、記述数はそれほど多くありません。漢字語句の出題割合が高くなっているのも特徴です。大問2題以外に、読解文が1題出題されています。
内容的には、説明文(随筆文)2000字程度、物語文3000字程度と他中学に比べても文章自体が長いのが特徴です。設問数も多く、時間内にきちんと解くためには、かなりの練習が必要となります。漢字については、書取りが多く出題されますから、十分練習をしておいてください。他の中学の単元別問題集(読解編)で過去問題を十分にトレーニングすることが必要です。付録には愛知県内の各中学に出題された漢字の全問題(過去11年)もついていますので、出題されやすい漢字を効率的に学習できます。要約問題が、本中学の特徴ですが、いかにはやく書くことができるかも、合否にかなり影響を与えています。朝日新聞の「天声人語」の出題が多いので、日ごろから読んで練習しておくとよいでしょう。
- 理科:傾向と対策
-
春日丘の理科の出題形式は、生物分野、物理分野、化学分野、地学分野が各大問1つで必ず出題され、多い場合は追加で1分野が追加される。
生物分野では、「環境」や「植物の成長・働き」「花のつくり」が、物理分野では「てこ・バネの問題」「運動」「電流・電磁石」「回路」が、化学分野では「水溶液(金属との反応・中和)」「溶解」、地学分野では「太陽と月」「天気・気温」などが中心に出題されている。また、教科書の単元から外れた出題も比較的多く出題される。昨年は「密度」の問題が出題された。
各分野の出題傾向がはっきりしているが、各分野の出題単元は毎年変化しているので、今年出題された単元は来年の入試では出題の可能性は少ない。そこを考えながら、受験期が近づいた時期は、広く浅く学習するよりも出題傾向からのポイント学習が効果が高い。
なお、実力を付けたい人には合格問題集「あとこれだけ」の「物理」「化学」「地学」などの各単元をピンポイントに利用すると良い。
- 社会:傾向と対策
-
社会では、歴史の大問1題、地理1~2題、政治1題が一番多い出題パターンといえます。歴史では、地理との融合問題も多くなっています。
内容的には、歴史は外交史を中心とする通史の出題が多くなっています。おもな歴史上の人名用語以外にも、記述問題が出題されます。それぞれの事件や用語を説明できるようにしておく必要があります。地理は、人口問題の出題が近年多くなっています。また、都道府県別の産業、特に工業などの出題が多いのも特徴といえますが、やはり全単元をきちんと学習しておく必要があります。政治は、日本国憲法を中心として、内閣・国会などの出題が目立っています。政治分野は、時事問題との関連も多いので、時事問題対策はしっかりとやっておきましょう(時事問題対策としては、12月初旬、時事対策問題がに入手できるようになっておりますので、ぜひともご利用ください)。