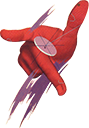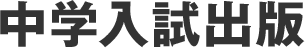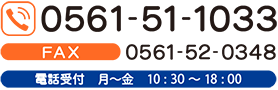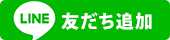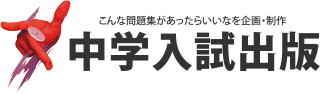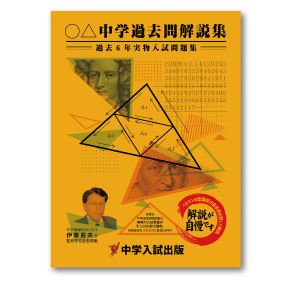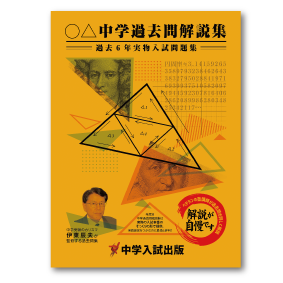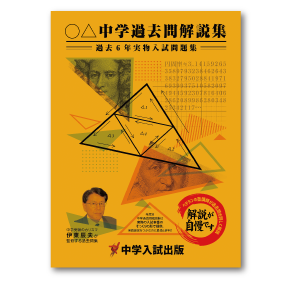洛星中学校
学校法人 ヴィアト-ル学園 洛星中学校
〒603-8342 京都市北区小松原南町33 TEL:075(466)0001
洛星中学は、昭和27年カトリック修道会によって創立された学校で、教育は、カトリックの世界観・人間観に基づき知・徳・体のバランスの取れた人間をつくることを基本としている。
生徒全員が大学進学を希望しているため、中高一貫の効果的な教科指導で、確かな学力を育むようなシステムになっている。主要5教科の時間数が多く、英語では外国人講師が担当している。週1時間の宗教の時間がある。
受験デ-タ-1:応募者数・実質倍率 (前期日程)
| 募集人員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
| R5年度 | 195人 | 444人 | 428人 | 256人 | 1.67倍 |
| R6年度 | 195人 | 471人 | 455人 | 245人 | 1.86倍 |
| R7年度 | 195人 | 461人 | 448人 | 241人 | 1.86倍 |
受験デ-タ-2:配点・試験時間
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | |
| 配 点 | 120点 | 120点 | 100点 | 100点 |
| 試験時間 | 60分 | 60分 | 50分 | 50分 |
| *3科受験生の総点は、3科合計点を44/34倍したものとする。 | ||||
受験デ-タ-3:受験者平均点・合格最低点
| 国 語 | 算 数 | 社 会 | 理 科 | 総合点 | 合格最低点 | 合格最高点 | |
| R5年度 | 67.5点 | 66.2点 | 76.3点 | 59.7点 | 264.3点 | 257.0点 | 363点 |
| R6年度 | 63.4点 | 76.4点 | 69.3点 | 61.2点 | 268.2点 | 265.3点 | 371.4点 |
| R7年度 | 59.8点 | 78.4点 | 73.0点 | 67.0点 | 275.3点 | 280.0点 | 365.0点 |
受験デ-タ-4:入試日程
【合格発表】 〔前期日程〕1月19日 〔後期日程〕1月25日
【願書受付】 〔前期日程〕12月9日~1月7日〔後期日程〕1月19日~22日
【受験料】 20,000円
洛星中学校 おすすめ教材
洛星中学校の出題傾向
- 算数:傾向と対策
-
洛星中学算数の出題傾向は、図形分野が38%で最も多く、次に文章題分野が16%である。整数分野が15%、計算分野が14%と他校と比べると比較的高いように思われるが、問題数が少ないため割合は高くなっている。割合分野も15%で、他校に比べると出題割合が高い。関数分野は2%であまり出題されない。まとめると、図形分野、割合分野、整数分野の出題が多く、文章題分野、関数分野の出題が少ないことが特徴である。
文章題分野では「仕事算」が多く、その他の単元は各単元がランダムに出題される。図形分野では「比を使った図形問題」が中心で、「図形の移動」「錘の問題」「多角形の面積」「角度」が続く。整数分野では「数列・規則性」、割合分野では「速さと比」が中心に出題される。計算分野では、「単位換算」が多い。
出題傾向ははっきりしているが、骨太の問題が多いので、しっかりと力をつけることが必要だ。難しい問題に時間をかけず、着実に標準問題を解くことが合否の分かれ目となる。なお、弱点補強には当出版発行の「単元別合格問題集(過去15年)」を是非ご利用下さい。過去15年間の入試問題がジャンル別に整理されています。また、関西難関校対象の「分野別問題集(図形・文章題)」なども是非ご利用下さい。 - 国語:傾向と対策
-
洛星の国語は、まず、文章が長い。そして、30字から150字以内で説明させたり、まとめさせたりする問題が必ず入ってくる。また、選択肢を選ぶ問題でも紛らわしい問題が出される。日頃から短時間で長文を読み、ポイントをまとめる練習が必要とされる。
また、読解問題では物語の登場人物の気持ちまで読み解くことも必要となることもあるので、日頃から登場人物の気持ちになって考えることを心がけておこう。
言葉の問題では、意味を聞く問題が出題され、かなり難しい言葉も出される。言葉の意味・イメ-ジなど日頃からチェックしておくとよい。
漢字の問題も10題出題されるので、確実にかけるようにしたい。
なお、漢字、ことわざ、文法、四字熟語などの漢字語句などの学習は当出版発行の難関漢字語句(中学受験用)を是非利用していただきたい。関西圏の難関中学の漢字語句問題が網羅されており、毎日短時間に学習するのに最適である。 - 理科:傾向と対策
-
洛星中理科の出題傾向は、物理分野が35%、化学分野が23%、生物分野が22%、地学分野が22%である。物理分野の出題割合が高く、他分野は均等に出題されていることが特徴である。また、以前は総合問題形式も出題されていたが、近年はあまり出題されていない。
単元別に見ていくと、生物分野では「人の体」の出題が多く、物理分野では「てこ・バネ」が中心で、近年は「回路」「電流・電磁石」も多く出題されている。化学分野では「水溶液関連の問題」「気体」「酸素・二酸化炭素」が中心に出題される。地学分野では「星の動き」「太陽と月」が多く、他単元はランダムに出題される。
物理分野では重心を使った「てこ」の問題や回転の問題、「圧力」の問題などの問題に、考えさせる問題も多い。難しい問題が必ず1問含まれており、簡単な問題との差が激しい。特に天体の問題や、「波」の問題等、初めて出会う問題に動揺しないことが必要だ。条件はすべての受験生に平等であるからだ。よく読み落ち着いて問題を解くことを心がけよう。
なお、弱点補強には当会発行の「単元別合格問題集(過去15年)」を是非ご利用下さい。過去15年間の入試問題がジャンル別に整理され、弱点補強に最適です。また、分野別問題集(物理・化学・地学)は関西難関中の各分野の問題を編集しており、入試直前には有効です。是非御利用下さい。 - 社会:傾向と対策
-
その年にもよるが、歴史の出題が半分近くを占めることが多い。歴史に関しては難問は少ないが、記述の問題が3~4問出題されので、日頃から記述の練習が必要だ。
また、地名やその位置などを問う問題もあり、地理との関連も押さえておきたい。
地理に関しては幅広い知識が問われるので、各県の気候・産業などの特色をしっかり勉強しておこう。また、教科書の統計資料・図版・地図などは最低限で、参考書などの資料集なども目を通すとよい。
時事問題も出題されるので、日頃からテレビのニュ-スや新聞などに目を向け、社会知識をつけるようにしておくことがよい。