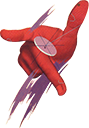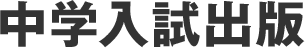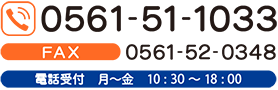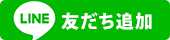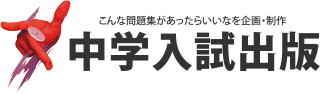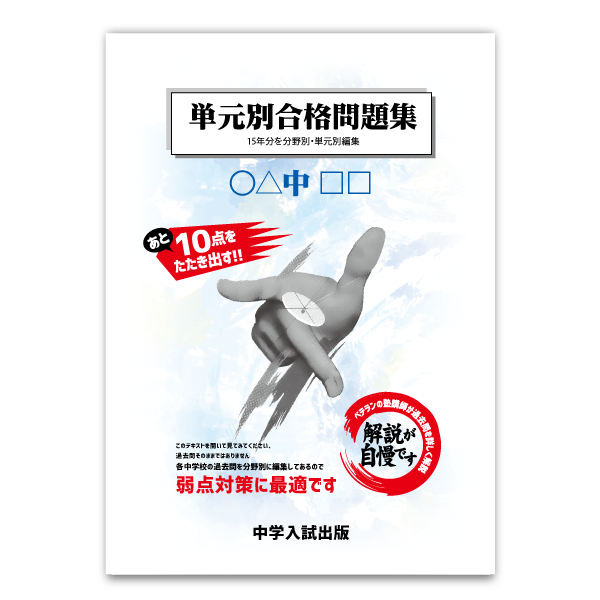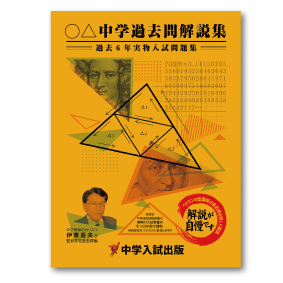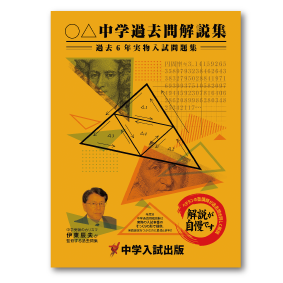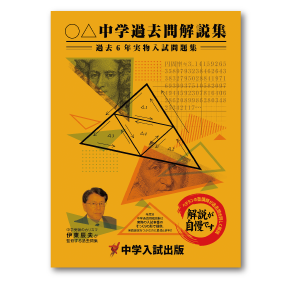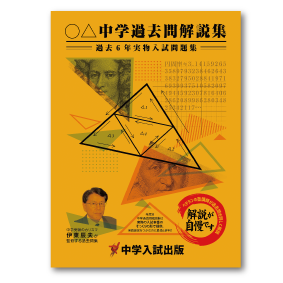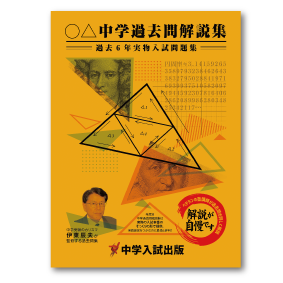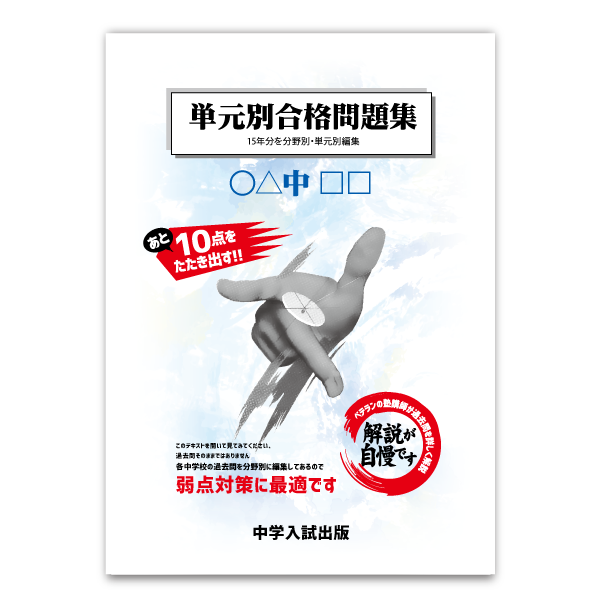六甲中学校
学校法人 六甲学院 六甲中学校
〒657-0015 神戸市灘区篠原伯母野山町2-4-1 TEL:078(871)4161
六甲中学は、イエズス会によって創立された学校で、カトリック的世界観・人間観に基づき、世界的な視野をもって国家・社会に貢献できる人間育成を教育方針としている。中高6年間の一貫教育によって、 勉学面では国際社会で活躍できるようより広い視野に立ち、より高度の学力養成に努めることで、トップ校の実績をあげ、また日常生活の面では、調和と実践力と思いやりをもった社会人へ導くことを目指している。
受験デ-タ-1:応募者数・実質倍率 (A日程)
| 募集人員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
| R4年度 | 145人 | 279人 | 253人 | 163人 | 1.55倍 |
| R5年度 | 145人 | 303人 | 283人 | 161人 | 1.76倍 |
| R6年度 | 145人 | 294人 | 275人 | 162人 | 1.70倍 |
受験デ-タ-2:配点・試験時間
| 国語 | 算数 | 理科 | |
| 配 点 | 150点 | 150点 | 100点 |
| 試験時間 | 60分 | 60分 | 50分 |
| 3科400点満点 | |||
受験デ-タ-3:受験者平均点・合格最低点(A日程)
| 国 語 | 算 数 | 理 科 | 3科総合点 | 合格最高点 | 合格最低点 | |
| R4年度 | 90.7点 | 73.8点 | 47.7点 | 212.2点 | 308点 | 199点 |
| R5年度 | 88.4点 | 70.2点 | 62.8点 | 221.4点 | 366点 | 213点 |
| R6年度 | 76.2点 | 95.5点 | 57.6点 | 229.3点 | 326点 | 224点 |
受験デ-タ-4:入試日程
【合格発表】 〔A日程〕1月14日 〔B日程〕1月17日
【願書受付】 WEB出願 12月15日~1月5日
【受験料】 20,000円
六甲中学校 おすすめ教材
六甲中学校の出題傾向
- 算数:傾向と対策
-
六甲中算数の出題傾向は、文章題分野が全体の35%の割合で、図形分野が31%で続きます。計算分野は18%と多いのですが、実質は小問2題が出題されるのみです。その他、整数分野が7%、割合分野が7%、関数分野が2%出題されています。文章題分野の出題が多いこと、整数分野が少ないことが特徴です。
文章題分野では「ジャンルに入らない問題」「速さの問題」が中心ですが、「場合の数」「相当算」「やりとり算」「食塩水」なども周期的に出題されます。図形分野では「比を使った図形問題(相似図形)」が圧倒的に多く、他は「多角形の面積」が中心です。割合分野では「速さと比」、計算分野では「□を求める」、関数分野では「区分関数」、整数分野では各分野がランダムに出題されます。
これらの単元を中心に対策を立てることが大切です。約2割の問題が若干難問で4割の問題が標準的な問題なので、難しい問題に時間をかけず、着実に標準問題を解くことが合否の分かれ目となります。近年は問題自体も易しくなっているため、計算ミスなどには十分注意していただきたい。
なお、弱点補強には当出版発行の「単元別合格問題集15年」をご利用下さい。 - 国語:傾向と対策
-
エッセイの読解、説明文の読解、物語文の読解、詩と鑑賞文の読解がバランスよく出題されていましたが、近年は長文は論説文(説明文)と物語文が中心で、漢字の書き取りが10題ほど出題されています。特徴的なことは、60字ほどの記述が2~3題出題されています。本校の過去問も含めて、問題集などで意識的に練習しておいたほうがよいでしょう。エッセイについては、それほど子供向けの内容ではなく、ごく一般的なレベルの文章が題材になっています。問題集や中学教科書なども参考に、例えば向田邦子さんや吉本ばななさんなどの、論理的な破綻のない名文家のエッセイに数多く触れておくとよいでしょう。大人にとっては常識でも小学生にはなじみのない事柄があるでしょうから、ぜひ家族の方は質問に答えるなど協力してあげてください。
以上の通り、癖のない出題になっているので、標準的な問題演習が有効な勉強方法であると思います。 - 理科:傾向と対策
-
六甲中理科の出題傾向は、生物分野が30%、地学分野が26%、物理分野が23%、化学分野は20%、実験・総合問題が1%です。生物分野、地学分野の出題が多く、化学分野が少ないですが、各分野がバランスがよいことが特徴です。
単元別に見ていくと、生物分野では「植物の成長・働き」が中心で、その他の単元はランダムに出題されています。物理分野では「てこ・バネ」、化学分野では「水溶液の中和・金属との反応」「溶解」、地学分野では「太陽と月」の出題率が高く、各分野はそれぞれの中心的な出題単元があり、他はランダムに出題される傾向である。比較的出題単元が特徴的なので、出題傾向に合わせた学習計画が功を奏するのではないでしょうか。
物理分野を中心に比較的難しい考えをさせる問題が出題されます。特に「てこ・バネ」「天体の問題」の問題などは十分過去問をこなして対策を立てましょう。
なお、弱点補強には当会発行の「単元別合格問題集(過去15年)」を是非ご利用下さい。